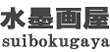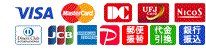Q 筆のおろし方と保存はどうするのですか?
ふのりで固められた穂を水にひたし、十分に水をふくませたら指でつまむようにのりを洗い流します。
毛先がほぐれたら指先ではさんで水を切り、毛先をきれいに揃えて乾燥させます。
使い終わったら、きれいな水で穂の根元までもみ洗いします。
強くしごくと根元の毛を折ることがあり、切れ毛の原因になるので注意が必要です。
洗い終わったら、穂先を整えよく乾燥させます。
穂先を下にして筆掛けに吊ってください。
画筆には紐がついていないものもありますので、そんな筆は洗濯ばさみで挟むか、筆立てにさしておきましょう。
移動には筆巻で巻いて、筆先を保護しましょう。
筆は湿気と虫くいが一番の注意点です。
購入時についているキャップは穂をいため湿気の原因にもなるので、外しておきましょう。
Q 水墨画で使われる付立筆、線描筆、面相筆の違いは?
水墨画は1本の筆でも描くことは可能ですが、表現方法によって使い分けることで、効果的な作画をえられます。
穂の腹を使った表現は付立筆、線表現は線描き筆、極細の線を表すときには面相筆とそれぞれ使い分けます。
付立筆の一般的な特徴
長所:穂にコシがあり、墨含みもよいので、穂先だけを使った表現や根元まで紙に押しつけて表す表現まで広く使えます。
短所:筆に不慣れな初心者が使うと、穂先のみを使った線表現の場合、思い通りの線質がえられません。
線描筆の一般的な特徴
長所:穂にコシがあり、穂先を使った細い線から穂の根元までを使ったやや太い線まで描けます。
短所:穂のコシを利かせるために、硬く墨含みが少ない毛を使っているので、面表現や長い線を表しにくいことがあります。
面相筆の一般的な特徴
長所:穂にコシがあり、穂先を使った極めて細い線が描けます。
短所:穂が小さく、墨をあまり多く含ませられないので、穂の腹まで使ったひょ玄には不向きです。
Q 色を塗りときは、どんな筆を使えばよいですか?
水墨画で色を塗るときに使う筆を彩色筆と言います。
この筆は色の確認に適した白色の毛が使われています。
毛の長さは短いですが、顔彩などの絵具をたっぷり含むことができるように毛の分量が多いつくりになっています。
材質は、羊毛が主体で、硬さに特徴のある馬毛が混じった筆であれば、コシが強いので、細い線が描きやすいです。
上記でご紹介した付立筆でも色塗りに使えますが、墨液の黒が混じって色が濁ることがあるので、彩色専用の筆を使う
のが無難です。
Q 筆の穂をイタめずに使うにはどうすればよいですか?
筆は適切な使い方をすれば長持ちします。
ケースごとに筆のメンテナンス法をお伝えします。
洗いきれずに固まってしまった筆
状態にもよりますが、ぬるま湯に10分ほどつけて、やさしくほぐします
穂が広がった筆
やさしく洗った後、タオルで包んで拭き取り、穂を整えます
整ったら、日陰の風通りのよい場所で掛けて乾かします
カビが生えた筆
湿ったまましまうと湿気でカビがはえることがあります
カビを生やさないためには、洗った後、日陰の風通しのよい場所に掛けて乾かします
筆筒や筆巻きで保管するのは、上記の状態で3日ほど乾かしてからにしましょう
Q イタめた筆はもう捨てるしかないですか?
まだ使えます。
イタんだ筆は通常の作画には使えないかもしれませんが、かすれが出やすいので、かすれを強調したいときに使うと便利です。
Q 筆の選び方の目安はありますか?
お店によっては試し書きが出来たり、穂を広げて確認することが出来ます。
それが出来ないようであれば、穂のカタチをみて選んでください。
穂全体がキレイな円錐形をしており、穂先が尖っているものを選んでください。
毛先のバランス
穂先を広げたとき、毛先がキレイに揃っている筆を選んでください。
筆の弾力
おろした筆であれば、穂の弾力も確認してください。
穂に力を加えたとき、ほどよいはね返りがあるのがよい筆です。
穂先のまとまり
試し書きの際、穂先が割れず、きれいにまとまるものを選んでください。
筆運びがなめらかかかどうかもポイントです。