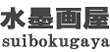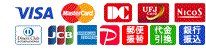水墨画道具は自分の使いやすい位置に置きましょう。
以下の画像のような配置がオススメですが、ご自分にとって使い勝手よくアレンジしてみてください。
絵皿や墨、硯など細かい道具はトレーなどに乗せておくと持ち運びに便利です。

墨
墨は煤・膠・香料の3種からできています。
水墨画は墨色が命ですから安価なものは避けた方がよいです。
墨には大きく分けて2種類あります。
松煙墨・・・青系黒の墨色でやわらかい表現に使います。
油煙墨・・・茶系黒の墨色で深みのある表現に適しています。
墨の良し悪しを見分けるのは難しいですが、磨っているときに墨が滑らかに動いて、墨液が漆黒になるものがよいです。
同じ大きさの墨の重さを比べたとき、重量の重いものより軽いものの方が良墨です。
水墨画用・書道用の墨の違い
膠の割合が違います。水墨画用の方が比較的膠が多く含まれています。
墨の重さ
1丁型で約15gです。
筆
はじめは長流の大からはじめられるのがよいでしょう。少しづつご自分にあった筆を見つけてください。
新しい筆は穂先を布海苔で固めていますので、水に浸して軽くつまむようにして布海苔をよく落としましょう。
筆の種類
| 号数 | 軸直径 | 穂直径 | 適性 | |
| 特大筆 | 16.5mm | 15mm以上 | 条幅用 | |
| 大筆 | 1号 2号 3号 4号 | 15.0mm 14.5mm 13.0mm 11.0mm | 13mm 12mm 11mm 9mm | 半紙1字書き 半切2行程度 半紙2字書き 半切2行程度 半紙4字書き 半紙6字書き |
| 中筆 | 5号 6号 7号 | 10.0mm 8.5mm 7.6mm | 8mm 7mm 6mm | 半紙6~8 字書き 仮名条幅 半紙8~12字書き 仮名条幅 半紙20 字書き 中字仮名 |
| 小筆 | 8号 9号 10号 | 6.7mm 6.0mm 5.5mm | 5.5mm 5mm 4.5mm | 一般書簡用 仮名細字 一般書簡用 仮名細字 一般書簡用 仮名細字 |
※あくまで目安です。
長さによる種類
| 超長鋒 | 柳葉(りゅうよう)ともいいます。根元の直径と穂の長さが7~10倍のもの |
| 長鋒 | 根元の直径と穂の長さが5倍以上のもの |
| 中鋒 | 根元の直径と穂の長さが4倍以上のもの |
| 短鋒 | 根元の直径と穂の長さが3倍以下のもの |
| 超短鋒 | 雀頭筆(じゃくとうひつ)ともいいます。根元の直径と穂の長さが2倍以下のもの |
製法・用法による筆のいろいろ
| 巻筆 | 芯毛を立てて薄葉紙を巻き、そのまわりに毛を植えて穂をつくった筆です。上世から明治初年まで多く使用されました。 |
| 固筆 | 巻筆にせず、穂の部分を文字通り穂型に糊固めした筆をいいます。昔は水筆と呼ばれていました。筆の職人さんは仕上筆と言っています。 |
| 捌筆(さばきふで) | 穂全体を糊固めせず、刷毛型に捌いた筆を捌き筆といいます。固筆をとるか捌き筆を取るかは使用者の好みによるところですが、捌き筆は固め筆よりも墨を含んだときの筆格好がわかりにくい面もあります。 |
| 真書筆 | 細字用の筆をそう呼びます。というのも、細字は楷書(真)で書かれることが多かったからのようです。細筆ですから、穂首にはだいたい1種類の毛を使い、混毛するにも2種類にとどめ、使いやすく2重筆管とするのが普通です。 |
| 面相筆 | 邦画で人物や仏像の面相を描くのに用いることが多いので、この名がつきました。イタチ毛や馬毛などの弾力性の大きい毛を使用しています。 |
| 隈取筆 | 邦画を描く場合、墨汁や顔料をぼかしための筆で刷毛に近いものです。この筆を作る際は柔軟で尖切れのない毛を揃え、穂尖をもっとも円満に捌くように心がけるそうです。 |
| 連筆 | 2本以上の筆を横に連ねて1本の筆にしている筆です。合筆とも連峰筆ともいいます。多くの場合、邦画を描くのに用いられます。 |
| 平筆 | 洋画用の筆で、軸端に金属片のついた穂先が平たい筆です。学校の絵画の時間に使っていたアレです。 |
| 刷毛筆 | 平筆を大きくしたもの、糊刷毛に似ているのでそう呼びます。 |
用毛の柔剛によるいろいろ
| 剛毛筆 | 同一の獣毛から作られた筆を指します。生え所によっては柔剛の差がありますから、その中に就いて剛毛を選び取って使用することも多いです。約7割程度まで使用したものを剛毛筆といいます。 |
| 柔毛筆 | 羊毛を使ったものが圧倒的に多いです。7割から10割の柔毛を使ったものを柔毛筆といいます。ちなみにウサギ・鹿・猫も柔毛です。 |
| 兼毛筆 | 文字通り剛・柔混ざり合った筆です。柔剛兼毛の仕方には、同一の獣毛から柔らかい部分と硬い部分を混ぜたものもあれば、別の獣毛を混ぜ合わせたものもあります。更に内側に柔らかい毛を用い、外側に硬い毛を配置する筆やそれとは逆に内剛外柔の筆など組み合わせの種類は様々です。 |
筆の保管
鑑賞用・由緒ある筆の場合
桐箱または豚皮製箱にナフタリン・樟脳・などを入れて湿気のないところに保管するのが良いです。
普段使いの筆
筆の根元まで一度墨をつけておくと防虫になります。洗ったのち、通気性の良い場所で筆架にかけたり、筆筒に差しておくと良いでしょう。
紙
国産の画仙紙・中国産の画仙紙・麻紙・玉版箋など。
水分を充分に吸収する手漉きの白い生紙がよいです。
画仙紙は紙質が弱く破れやすいのですが、墨をよく吸収することから渇筆が自然に表現でき、墨色も美しくでます。
硯
中国のものが上質で、大きめの安定感のあるものがオススメです。
硯は墨をするのになくれはならない用具ですが、硯の良し悪しで、すった墨の墨色が良くも悪くもなりますので、やはり選び方には充分注意が必要です。
硯石はめったにない貴重なもので、その辺の石なら何でも良いというわけにはいきません。
墨をおろす硯は、あまり硬くてつるつるではいけませんし、石の粒子が粗く、すった際に墨と石質が混じってしまうようではよい硯とはいえません。
ほどよい硬さで、石質がするとけることなく、墨がほどよくおろせるものでなければなりません。
そのためには、石の中の鋒鋩というものが、ほどよく混じり合っていなければならないのです。
鋒鋩とは、石英や銅、鉄などの小さな結晶で、これが墨をする際におろし金のような役割を果たしています。
鋒鋩があまり粗く、たくさんありすぎると、墨が早くおりる代わりに、ドロリとしてしまいます。
反対に、鋒鋩が細かすぎると、いつまで磨っても墨がおりず、つややかな墨色が出ないこととなります。
下敷き
白のフェルトがオススメです。
はじめて購入される際は必要無いと思われるかもしれませんが大きめのものを求められるのがよいでしょう。
紺など色のあるものを敷くと紙が塗れているときの墨色が分かりにくいので白が最適です。